Summary
Key Points:
原文の要点
Seit der Einführung der blauen Haken bei Twitter sind sie heiß begehrt. Diese Verifizierungssymbole, die eigentlich ein weißer Haken auf blauem Grund sind, wurden bisher an 187.000 Profile vergeben. In Workshops wird oft betont, dass ein blauer Haken die Echtheit des Absenders bestätigt. Doch was, wenn der Workshopleiter selbst keinen blauen Haken hat? Sollten die Teilnehmer ihm dann vertrauen? Auch gab es immer wieder Diskussionen darüber, warum manche Personen einen blauen Haken erhalten, während andere leer ausgehen. Die Regeln schienen je nach Land oder Branche unterschiedlich ausgelegt zu werden. Doch das gehört nun der Vergangenheit an: Twitter hat vor kurzem bekannt gegeben, dass jeder Nutzer einen blauen Haken beantragen kann. Dafür müssen ein Foto, eine Biographie und Kontaktdaten hinterlegt werden, sowie ein Grund angegeben werden, warum das Profil verifiziert werden sollte. Nicht jeder Account wird automatisch verifiziert, sondern nur solche, die von öffentlichem Interesse sind, wie etwa Profile von Prominenten, Organisationen oder Personen aus Bereichen wie Musik, Politik, Journalismus oder Sport. Der Verifizierungsprozess ist einfach: Man prüft, ob das Profil in Frage kommt, startet den Prozess und wartet auf die Entscheidung von Twitter. Verifizierte Accounts erhalten zudem Zugriff auf neue Funktionen, wie das Filtern von Erwähnungen. Es bleibt abzuwarten, wie großzügig Twitter mit der Vergabe der blauen Haken umgehen wird. Für Journalisten wäre es wünschenswert, wenn möglichst viele Profile verifiziert würden. Ein Tipp am Rande: Wer regelmäßig Updates aus dem Netz direkt zum Frühstück erhalten möchte, kann den persönlichen WhatsApp-Service des Autors nutzen.
回想
あの頃、Twitterの青いチェックマークについての記事を書いた時のことを思い出すと、なんだか懐かしい気持ちになる。当時は、この「青いチェックマーク」がすごく話題になっていて、誰もが欲しがっていたよね。私もその熱狂の中にいて、記事を書くためにいろいろ調べたんだ。特に印象的だったのは、ワークショップで「青いチェックマークは送信者の信頼性を保証する」と強調されていたのに、その講師自身がチェックマークを持っていないという矛盾。参加者は彼を信じていいのか?って思っちゃった。
それに、なぜある人はチェックマークをもらえて、別の人はもらえないのか、という議論もよく耳にした。国や業界によってルールの解釈が違うんじゃないかって感じてたけど、それが今では過去の話になったんだよね。Twitterが「誰でも申請できる」って発表した時は、正直ちょっと驚いた。でも、結局は「公共の利益にかなう」アカウントだけが認められるってことで、やっぱりハードルは高いんだなって思った。
記事を書いている時は、この新しいシステムがどうなるのか、Twitterがどれだけ寛大にチェックマークを配るのか、ってことを考えながら書いてた。特にジャーナリストにとっては、できるだけ多くのプロフィールが認証されることが望ましいって感じてたね。
あと、最後にちょっとした宣伝を入れたのも覚えてる。WhatsAppのサービスを紹介したんだけど、あれは結構反応が良かったんだ。朝ごはんと一緒にネットの最新情報をチェックできるって、便利だよね。
今振り返ると、あの記事は当時のTwitterの変化をリアルタイムで追いかけていた感じがする。書いている時は、読者がどう感じるか、どう伝えるかってことをすごく考えてたな。あの頃の熱気や興奮が、今でもちょっと蘇ってくる気がする。
それに、なぜある人はチェックマークをもらえて、別の人はもらえないのか、という議論もよく耳にした。国や業界によってルールの解釈が違うんじゃないかって感じてたけど、それが今では過去の話になったんだよね。Twitterが「誰でも申請できる」って発表した時は、正直ちょっと驚いた。でも、結局は「公共の利益にかなう」アカウントだけが認められるってことで、やっぱりハードルは高いんだなって思った。
記事を書いている時は、この新しいシステムがどうなるのか、Twitterがどれだけ寛大にチェックマークを配るのか、ってことを考えながら書いてた。特にジャーナリストにとっては、できるだけ多くのプロフィールが認証されることが望ましいって感じてたね。
あと、最後にちょっとした宣伝を入れたのも覚えてる。WhatsAppのサービスを紹介したんだけど、あれは結構反応が良かったんだ。朝ごはんと一緒にネットの最新情報をチェックできるって、便利だよね。
今振り返ると、あの記事は当時のTwitterの変化をリアルタイムで追いかけていた感じがする。書いている時は、読者がどう感じるか、どう伝えるかってことをすごく考えてたな。あの頃の熱気や興奮が、今でもちょっと蘇ってくる気がする。
Extended Perspectives Comparison:
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 青いチェックマークの意味 | Twitterでの信頼性を示すシンボル |
| 申請対象者 | 公共の利益にかなうアカウント(有名人、団体など) |
| 申請手順 | 写真、プロフィール、連絡先情報、理由を提出する |
| 影響範囲 | 認証されたアカウントは新機能へのアクセスが可能 |
| ジャーナリストへの影響 | 多くのプロフィールの認証が望ましい |
Reference Articles
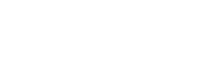

 ALL
ALL 住宅リフォーム
住宅リフォーム
Related Discussions